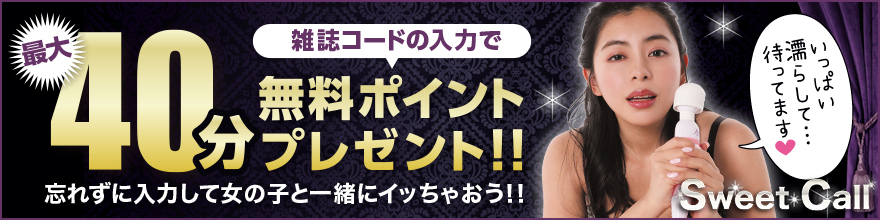繰り返される焼失と復興、何度でも立ち上がる野心。
遊郭から赤線、ソープ街へと風俗の王道を歩く日本一の色街。
トルコ風呂の進出が街の運命を決めた
売春防止法施行により、赤線からトルコ風呂街になった吉原と、遊郭の流れをそのまま残す飛田新地、日本の二大風俗街の歴史の変換点に迫る。
日本橋から浅草へ移転した吉原の歴史
現在、台東区千束にある「吉原」の歴史は江戸時代まで遡る。1617年、幕府により日本橋人形町に「葭原 ( よしはら) 遊郭」として開郭されたが、1657年、明暦の大火により消失、現在の地へ移転した。その後も、関東大震災や東京大空襲などで被災したが、そのつど復興し、戦後は赤線へと移り変わった。当時、吉原では1200人の遊女が働き、料金はショートが300~1000円、泊まりが1200円前後。大卒の初任給が五千円の時代であるが、現在の価値に換算しても、そう変わっていないことがわかるだろう。
銀座から吉原へトルコ風呂の歴史
その頃、ニッポンの風俗界に大変革が起きようとしていた。売春防止法(1958年、以下売防法)の制定である。これにより、日本各地にあった赤線は、旅館や料亭街などへ転業せざるを得なくなっていた。その時、「吉原」が選択したのは、当時、ブームとなりつつある「トルコ風呂」だった。
「トルコ風呂」は、1951年、銀座に一号店ができて以来、徐々に人気が上がり始め、売防法施行から3ヶ月後、吉原に「吉原トルコ」が開店するや、元赤線業者がこぞってトルコ風呂への転業を始めたのだ。
1960年には16軒だったトルコ風呂は、東京オリンピック開催の前年(63)から急増し、75年には65軒、80年には150軒へと急増している。国際イベントを契機に店舗数を伸ばしたのは、現在とは真逆である。そして、1984年、トルコ人留学生の嘆願により、名称が「トルコ風呂」から「ソープランド」へと変わることになった。
遊郭を残すため飛田がとった道
新業種の「トルコ風呂」に活路を見出した吉原に対し、同じ頃、大阪の飛田遊郭では、多数の特殊飲食店が、旧来同様の商売を貫く方針を固めていた。
飛田遊郭の歴史は明治期に始まっている。1912年(明治45年)、難波新地にあった乙部遊郭が火災により消失すると、そこにいた業者が移転して現在の地で「飛田遊郭」が始まった。吉原と違うのは、空襲の戦火から逃れたせいで、今でも当時を忍ばせる建物が残る町の雰囲気だろう。
その飛田遊郭が、売防法施行の下、選んだのは意外な道だった。
当時、約200軒あった特殊飲食店は、売防法施行前の2月に廃業届を提出し、その内の55軒が翌月の3月には料亭として届出を提出したのだ。その理由は、それまでの遊女たちを芸妓に仕立て、料亭へ派遣する花街として復活の道を選んだのだった。
東西二大風俗街の大きな共通点
しかし、置屋から呼ばなくてはならない煩わしさが不評となり、そこで当時、難波などで人気となっていた「アルバイトサロン(以下アルサロ)」を真似て、遊女を仲居として店の玄関に待機させるようにした。すると、これがウケた。
「アルバイト料亭」の人気の理由はもう一つあった。飲み物とおつまみが付いて15分ワンセットという明朗会計である。これは、現在の飛田新地の遊び方と同じである。違うのは、当時は多くの客が2セットで遊んでいたことと、布団ではなく、座布団を並べて敷いていたところである。
売防法施行から約60年が経過した現在、巨大ソープランド街を形成した東京・吉原と、現在も昭和初期の面影を残す遊郭が残る街、大阪・飛田新地は、互いに違う業種で生き残っている。
吉原はなぜ、遊郭として残らなかったのか? 飛田はなぜトルコ風呂を受け入れなかったのか? を考えるよりも、「それぞれがそれぞれの地域で受け入れられる道を選んだ」と考える方が自然である。
そして、ニッポンの二大風俗街が半世紀以上も続いていられる理由は、それぞれの街が定める厳格な規律をマジメに遵守することと、「客と仲居の自由恋愛」という、曖昧な建前文化の恩恵に違いはないようだ。